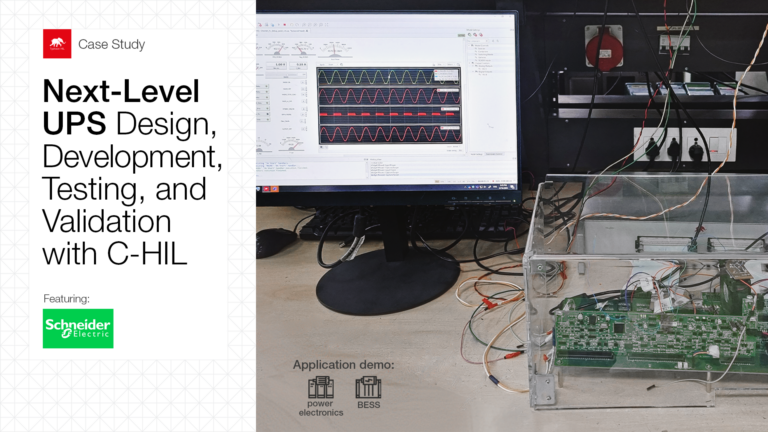首都大学東京パワーエレクトロニクス研究室でのご研究内容について教えてください。
和田教授|パワーエレクトロニクスの回路、回路、要素技術の応用範囲は幅広く、特定の分野に特化するのではなく、可能な限り幅広い基盤技術を網羅し、それらの技術をどのように応用できるかを考えるようにしています。企業との共同研究はもちろんのこと、研究室内での独自の研究も日々行っています。
他大学との共同研究も行っているのですか?
和田教授|はい、もちろん他大学との共同研究は行っています。ただし、他の研究室と共同研究を行う場合は、研究の責任を分担できるよう、異なる分野を専門とする先生方と連携するよう努めています。
共同研究されている教授陣の専門分野は何ですか?
和田先生|モーターや集積回路、パワーデバイスなどを専門とする先生方はもちろん、数値計算や生物学など電気とは全く関係のない先生方まで、幅広い方々と共同研究を行っています。
あなたの研究室で現在流行している研究テーマは何ですか?
和田教授|SiC(炭化ケイ素)やGaN(窒化ガリウム)を用いたコンバータは、現在も多くの研究課題が進行中だと感じています。回路図通りに回路を組むのではなく、最高の性能を引き出すためにはどうすればよいかを考えることが重要だと考えています。最近は異分野融合についても考えており、パワーデバイスや受動部品など、自分の専門分野以外の分野の方々と連携し、今後新たな研究テーマを切り拓いていきたいと考えています。
関口様|私の専門は太陽光発電(PV)研究なので、電力システム関連の動向をチェックしています。最近は分散型電源(DER)を大量に導入すると系統全体の不安定化が懸念されています。分散型電源の大量導入は系統の慣性不足につながるため、慣性を生み出す分散型電源向けの系統形成インバータの研究が多いと感じています。
分散電源用のグリッド形成インバータに関する研究は数多く行われています。

関口さんの研究について詳しく教えてください。
関口さん|私の専門は太陽光発電(PV)研究で、特にPVパワーコンディショナの効率向上と長寿命化に焦点を当てています。PVシステムで発生する可能性のある課題の一つに、PVアレイへの部分的な影が発電効率に影響を与えるという問題があります。私の研究目標は、電解コンデンサの寿命を延ばすアクティブパワーデカップリングおよび制御手法を統合することで、高いPV効率と長寿命化を実現することです。
ハードウェア・イン・ザ・ループ (HIL) について初めて知ったのはいつですか?
和田教授|約10年前、海外の大学の研究室を見学した時のことです。そこでHILが広く活用されているのを目の当たりにし、パワーエレクトロニクス分野にも応用できることを知りました。当時から、回路シミュレーション(SIL:Software-in-the-Loop)から実機へのジャンプはハードルが高いと感じていましたが、正直、当時はHILを実際に試す機会がありませんでした。
しかし、少し前、新型コロナウイルス感染症のパンデミックによるロックダウンで、学生が大学の研究室に入れない期間が数ヶ月ありました。それまでは、回路シミュレータを使ってシミュレーションを行い、それを実機で繰り返すという流れが一般的でしたが、研究室に常時アクセスできないため、実機を使った実験は不可能でした。清水先生が購入していただいたTyphoon HIL装置があったので、自宅で実験してみようと考えました。
自宅では実機を使った実験はできず、シミュレーションしかできなかったので、HILシステムをもっと活用していくには絶好の機会だと思いました。当時、関口さんは博士課程1年生だったので、ある意味、新しいチャレンジをするにはちょうど良いタイミングでした。
在宅勤務中は実機での実験はできず、シミュレーションのみしかできなかったため、HILシステムをより積極的に活用していく絶好の機会だと思いました。
HIL はパワーエレクトロニクスシステムの検証に効果的なツールだと思いますか?
和田教授|はい。
HILは特定の研究分野においては扱いが難しい場合もありますが、基礎研究や主要なアイデアの検証においては非常に有効だと考えています。近年、学会におけるHILを用いた論文が増加しており、一部の学術誌ではHILの有用性を認める方針が明記されています。
かつてはパワエレは実機での検証しかないという風潮がありましたが、今では「ここまではHILでテストすれば十分」といったように、HILを使える線引きを関口さんと議論しているところです。
近年、学会でもHILを活用した論文が増えてきています。
関口さんご自身の研究で、Typhoon HILをどのように活用されているのでしょうか?
関口様|PVアプリケーションにおける能動電源分離回路方式については、既に様々な研究が行われているため、私は制御部分に注力しています。回路シミュレータの一般的な問題点として、シミュレーションに時間がかかることが挙げられます。回路側が完成していれば、HILで制御を検証し、その反応を見てすぐに新たな試みに挑戦する方がよいため、現在はTyphoon HILを活用しています。
HILで基本的な検証を行えば、制御プログラムは実機でも問題なく動作します。実機で動作しない場合は回路側に問題があると想定し、問題と思われる回路部分をHILで再現することで迅速に修正できます。Typhoon HILは、シミュレーション環境から実機での実験へスムーズに移行するために活用されています。
Typhoon HIL は、シミュレーション環境から実際のデバイスでの実験へのスムーズな移行に使用されます。
実際のデバイスに移行する前に、SIL だけでなく HIL で検証したほうがよいと思いますか?
関口さん |はい、そうします。
シミュレーションを用いて制御を検証する学生は、マイクロコントローラの物理的なメカニズムを理解していないことがよくあります。シミュレーションからすぐに始めるよりも、実機に近い環境でHILを用いた制御検証を始める方が、学生にとってスムーズだと思います。

HIL の最大の利点は、リアルタイムで応答することです。
Typhoon HIL セットアップの使用を開始するまでにどれくらいの時間がかかりましたか?
関口様|Typhoon HILをゼロから使い始めるには、回路シミュレーションなどに慣れていることが前提となりますが、1週間もあれば十分だと思います。マイコンの学習も含めると、HILとマイコンのI/Oの接続も含めて、1~2ヶ月程度で全て完了できると思います。
Typhoon HIL の起動時に問題が発生しましたか?
関口様|使用しているマイコンのI/Oを調べるのに時間がかかり、接続に少し苦労しました。しかし、Typhoon HILデバイス自体のデジタルI/OとアナログI/Oは分かりやすかったです。
Typhoon HIL を使用したことでどのようなメリットがありましたか?
関口様|HILの最大のメリットは、リアルタイム性です。PVの最大電力追従制御(MPPT制御)の検証には長いシミュレーション時間が必要で、HILシミュレーションは半日程度かけて行いました。SILで半日シミュレーションを行おうとすると、膨大な計算時間がかかってしまいます。その点、HILは工数と時間削減の面で非常に有利です。リアルタイム性が高いため、検証にかかる時間が大幅に短縮されます。
HILは工数と時間の節約という点で非常に有利です。リアルタイムで応答するため、検証プロセスにかかる時間が大幅に短縮されます。
パワーエレクトロニクスにおいて、HIL が最もよく使用されるアプリケーションはどれだと思いますか?
和田教授|電力系統やグリッドへの接続(統合)においては、HILを用いた検証が非常に有益になると思います。これまでは、電圧と電流を検出して計算し、使用するインバータを決定するのが一般的でした。
今後、大規模システムの研究はますます発展し、将来のインバータ設計にも影響を与えていくと考えています。通信速度の向上に伴い、時間遅延や通信途絶といった様々な問題が重要となるため、HILは実際の計算資源や通信資源を活用しながら、インバータに制御が適用可能かどうかを検証するのに非常に適しています。特に、日本だけでなく欧米においても、電力の有効活用は今後の避けられない課題であり、HILが果たす役割は非常に重要になると考えています。

クレジット
オリジナルインタビュー| MyWayウェブサイトで日本語版がご覧いただけます。
インタビュアー|杉山勇 (MyWay)
翻訳| セルジオ・コスタ、デボラ・サント
ビジュアル| 写真はMyWayが撮影し、Karl Mickeiが編集しました。
編集者| デボラ・サント